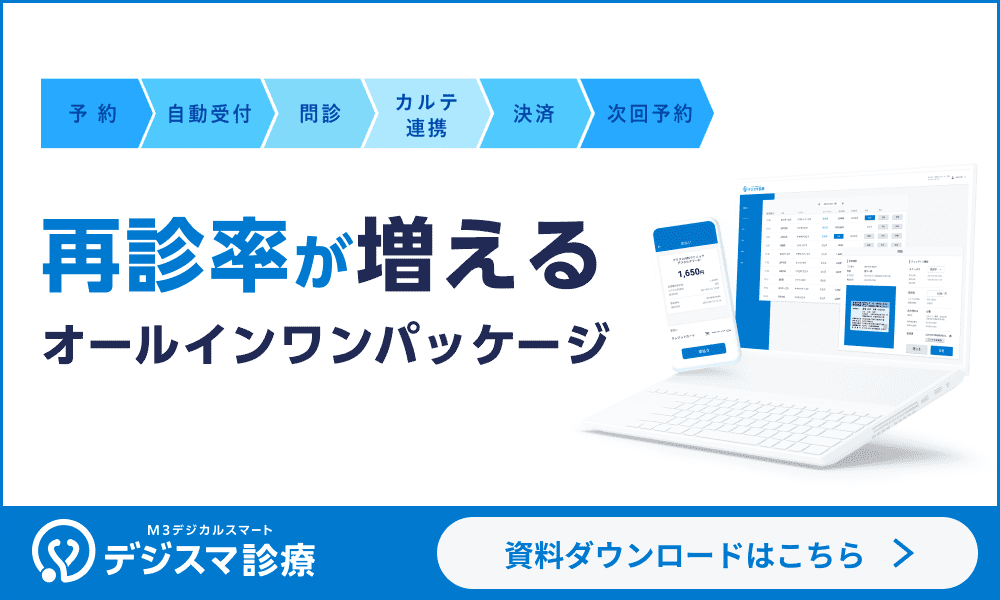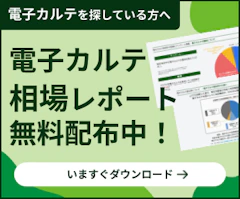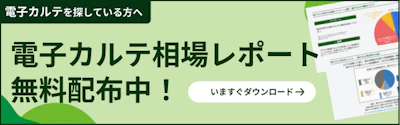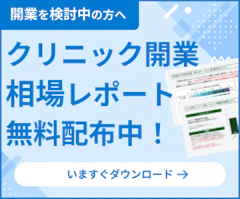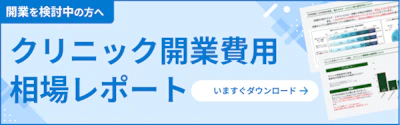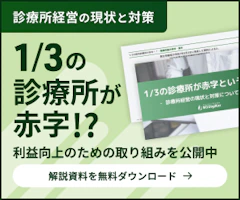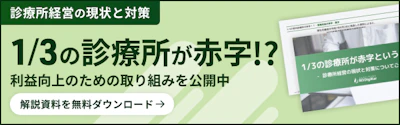AI搭載の電子カルテ6選。効果やメリット・デメリット、選び方や導入のポイントも解説
2025年08月30日 更新日: 2026年01月28日
「電子カルテ」と聞いて、どのようなイメージをお持ちでしょうか?手書きの紙カルテからデジタルへと移行する動きが加速する中、電子カルテは業務効率化や医療安全の向上に欠かせないツールとなっています。特に近年、AI(人工知能)を搭載した電子カルテが登場し、その機能は飛躍的に進化しています。本記事では、電子カルテ導入の基本から、AIがもたらすメリット、そして最新のAI搭載電子カルテのおすすめ製品まで、具体的な事例を交えながら徹底解説します。最適な電子カルテ選びにお悩みの方は、ぜひご一読ください。
目次
電子カルテの概要
現代の医療現場では、テクノロジーの進化が日々の診療に大きな変革をもたらしています。その中心にあるのが電子カルテです。手書きの紙カルテからデジタルへと移行することで、医療機関は業務効率の向上、医療安全の強化、そして患者サービスの質の向上といった多岐にわたるメリットを享受しています。
電子カルテの普及率
厚生労働省の調査(令和5年時点)によると、電子カルテの普及率は年々増加しています。病院では既に65.6%、クリニックでは55.0%の施設で導入済みです(※)。政府は医療DX令和ビジョン2030において、2030年までに電子カルテの普及率100%を目標に掲げており、今後も導入が加速する見込みです。
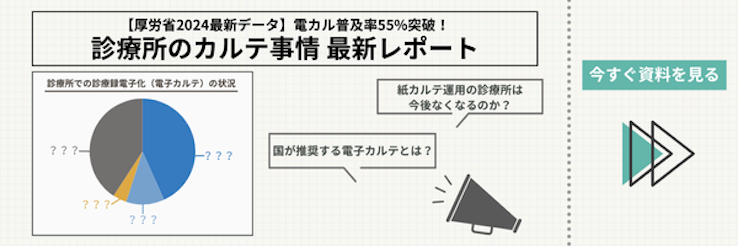
電子カルテのメリット
電子カルテを導入することで、クリニックは多くのメリットを享受できます。
- 業務効率の向上:
手書きカルテの記入、保管、検索にかかる時間を大幅に短縮できます。レセプト作成も自動化され、事務作業の負担が軽減されます。 - 医療安全の向上:
判読性の高いデータで記入ミスや読み間違いが減り、医療事故のリスクを低減します。アレルギー情報や禁忌薬の自動警告機能なども活用できます。 - 情報共有の円滑化:
医師、看護師、医療事務などのスタッフ間でリアルタイムに患者情報を共有できます。これにより、チーム医療が促進されます。 - 経営状況の把握:
診療データがデジタル化されるため、疾患別、月別などの集計・分析が容易に行えます。これにより、経営改善のための具体的な施策を検討しやすくなります。 - 省スペース化:
紙カルテの保管場所が不要になり、クリニック内のスペースを有効活用できます。 - 患者サービスの向上:
待ち時間の短縮、オンライン予約システムの導入、オンライン診療の実施などにより、患者さんの利便性が向上します。 - 災害時対策:
クラウド型電子カルテであれば、災害時にもデータが保護され、別の場所からアクセスできるため、診療の継続性が確保されます。
電子カルテのデメリット
一方で、電子カルテ導入にはいくつかの課題も存在します。
- 初期費用と月額費用:
システム導入には初期費用や月額費用がかかります。PCや周辺機器の購入費用も考慮する必要があります。 - 操作習熟までの時間:
電子カルテの操作に慣れるまでに、医師やスタッフの一定の学習期間が必要です。 - システムトラブルのリスク:
システム障害やネットワークトラブルが発生した場合、一時的に診療が滞る可能性があります。クラウド型の場合はインターネット環境に依存します。 - 情報漏洩のリスク:
サイバー攻撃やヒューマンエラーによる情報漏洩のリスクがゼロではありません。セキュリティ対策が重要になります。 - 停電時の対応:
停電が発生した場合、システムが利用できなくなる可能性があります。緊急時の対応策を検討しておく必要があります。 - 法改正への対応:
医療に関する法改正があった場合、電子カルテシステムもそれに合わせてアップデートされる必要があります。ベンダーの対応力を確認することが重要です。
また、紙カルテから電子カルテへの乗り換えをご検討されている先生へ、電子カルテ普及率100%時代に向け意識すべき点などをまとめた資料を無料でお配りしておりますのでお気軽にご覧ください。
資料閲覧はこちら:紙カルテをご使用中の方必見!2030年電子カルテ普及率100%?
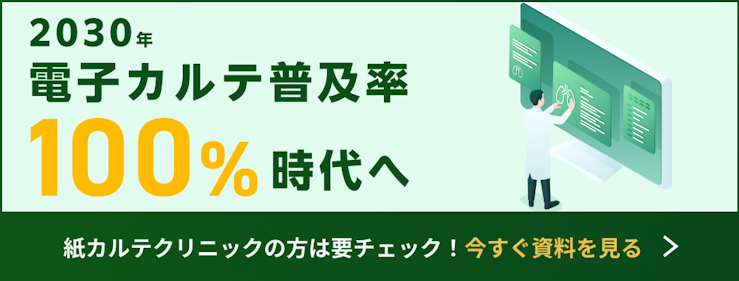
AI搭載の電子カルテ活用のメリット
近年、電子カルテにAI(人工知能)が搭載されることで、その機能は飛躍的に向上しています。AIは医師や医療スタッフの業務を強力にサポートし、診療の質と効率を一層高めます。
オーダーレコメンド
AIが過去の診療データや患者の症状、検査結果などを分析し、次に必要となる処方や検査、病名などのオーダーを自動で推奨してくれます。これにより、医師は適切な医療行為を迅速に選択でき、入力漏れや判断ミスを防ぎながら、診療時間を大幅に短縮できます。
文章サマライズ
診察中に医師が入力した膨大なカルテ情報や、過去の診療記録から、AIが重要な情報だけを抽出し、簡潔な要約(サマリー)を自動で作成します。これにより、多忙な医師が患者の状態を短時間で把握できるようになり、カンファレンスや情報共有の効率が向上します。
その他入力サポートツール(文字起こし、問診)も
AIは電子カルテ本体だけでなく、連携する外部サービスを通じて、さまざまな入力作業を支援します。
- 音声入力・文字起こし: 診察中の会話や医師の口述をAIがリアルタイムで認識し、自動でテキスト化します。カルテの手入力の負担が減り、診察に集中できる環境を整えます。
- AI問診: 患者の回答からAIが判断し、問診内容を動的に変更することで、医師は事前により詳細な情報を把握できます。診察時間の短縮や、問診の質向上に繋がり、医師の負担を軽減します。
AI搭載の電子カルテの選定ポイント
AI搭載の電子カルテは、その先進性ゆえに選び方や導入において考慮すべきポイントがいくつかあります。自院のニーズに合った最適なシステムを選ぶために、以下の点をチェックしましょう。
選定ポイント1:AIで課題が解決できるか
まず、自院が抱えている具体的な課題をAIがどのように解決できるかを明確にしましょう。
- 「カルテ入力に時間がかかっている」「レセプトチェックのミスが多い」といった業務効率の課題でしょうか?
- それとも「診療の質を向上させたい」「エビデンスに基づいた最新の治療情報を手軽に得たい」といった医療の質の課題でしょうか?
AIの機能は多岐にわたるため、自院の困りごとをAIが持つどの機能で解決できるのかを具体的にイメージすることが重要です。
選定ポイント2:その他の操作性がよいか
AI機能だけでなく、電子カルテとしての基本的な操作性も非常に重要です。
- 直感的なUI/UX: 毎日使うシステムだからこそ、誰でも簡単に直感的に操作できるかを確認しましょう。
- 入力方法の多様性: 音声入力や手書き入力、定型文入力など、AI以外の入力補助機能も充実しているかを確認してください。
- 画面の見やすさ・カスタマイズ性: 診療スタイルに合わせて画面をカスタマイズできるか、必要な情報がスムーズに表示されるかも確認ポイントです。
選定ポイント3:サポート体制が充実しているか
AI搭載の電子カルテは比較的新しい分野の製品も多いため、導入から運用までを支えるベンダーのサポート体制は特に重要です。
- 導入時のサポート: AI機能の設定や初期学習に関する専門的なサポートがあるかを確認しましょう。
- 運用後のサポート: AIの精度改善に関するフィードバック対応や、トラブル発生時の迅速な対応体制が整っているか。
- 法改正への対応: 医療に関する法改正やAI技術の進化に合わせたシステムアップデートが継続的に行われるかどうかも、ベンダーの対応力を確認する上で重要です。
選定ポイント4:料金が適正か
AI搭載電子カルテの料金は、製品によって大きく異なります。初期費用と月額費用の両方を考慮し、長期的な視点での費用対効果を検討しましょう。
- AI機能の料金体系: AI機能が標準搭載されているのか、オプションで追加料金が発生するのかを確認しましょう。
- トータルコスト: システム本体費用だけでなく、ハードウェア費用、データ移行費用、サポート費用など、全てを含めた総コストで比較検討しましょう。
- 費用対効果: AI導入によって得られる業務効率化や医療の質向上といったメリットが、コストに見合うか評価することが重要です。
また、電子カルテを導入するにあたって、約800名の開業医にアンケートを行い導入費用やランニングコストを調査したレポートを無料でお配りしておりますのでお気軽にご覧ください。
資料閲覧はこちら:クリニック向け電子カルテ費用相場レポート
38.1cm%C3%9713.23cm.png)
AI搭載の電子カルテのおすすめ6選
ここでは、AIを搭載している、またはAIとの連携に強みを持つおすすめの電子カルテを6製品ご紹介します。
※各電子カルテの情報は2025年8月時点のものです。
エムスリーデジカル/M3DigiKar(エムスリーデジカル)
エムスリーデジカルは、医療情報サイト「m3.com」を運営するエムスリーグループが提供するクラウド型電子カルテです。高い操作性と豊富な機能、そして最新のAI技術を活用した業務効率化機能が特徴で、近年特にクリニックからの支持を集め、急速にシェアを拡大しています。
エムスリーデジカルの主な特徴
- 直感的な操作性:
洗練されたUI/UXで、電子カルテの操作に不慣れな方でもスムーズに導入・利用できます。タブレットでの手書き入力や音声入力にも対応し、医師の負担を軽減します。 - AIによる業務支援:
患者ごと、医師ごとのよく利用するオーダーを学習しリストに表示するなど、AIを活用した機能が充実しています。これにより、診察時間の短縮や医療の質の向上に貢献します。 - 「デジスマ診療」とのスムーズな連携:
WEB予約・WEB問診・自動受付・キャッシュレス決済・お知らせ配信・オンライン診療の機能などがオールインワンになった「デジスマ診療」と連携し、患者さんの予約から診察、会計までを効率化。 - 充実した周辺システム連携:
オンライン診療システム、Web予約システム、Web問診システム、検査システムなど、クリニック運営に必要な様々なシステムとの連携が可能です。 - 強固なセキュリティ体制:
医療情報を扱うため、厳重なセキュリティ対策が施されています。データはクラウド上で管理され、災害時のリスクも低減されます。 - レセコン一体型:
レセプトコンピュータが標準で搭載されており、レセプト作成業務を効率化します。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 0円~ |
月額費用 | 11,800円~(ORCA連動型)、24,800円~(レセコン一体型)※いずれも税別 |
運営会社 | |
システム形態 | クラウド型 |
AI機能 | AI自動学習機能 |
導入サポート | 専任スタッフによる導入前コンサルティングから導入後のサポートまで手厚い支援 オンライン説明会、セミナーも実施 |
周辺システムとの連携・拡張性 | 充実した周辺システム連携 |
レセコン | レセコン一体型/ORCA連動型 |
その他、詳しい導入事例や料金プランを確認したい方はこちら

また、エムスリーデジカルは無料で操作性を体験することができます。こちらからご登録ください。
Brain Boxシリーズ(ユヤマ)
Brain Boxシリーズは、医療機器メーカーであるユヤマが提供する電子カルテです。豊富な医療機器との連携実績があり、クリニックの設備環境に合わせた柔軟なシステム構築が可能です。AIによるオーダー分析や問診内容分析など、業務を効率化する機能を搭載しています。
Brain Boxシリーズの主な特徴
- AIによるオーダー分析: オーダー内容をAIが自動分析し、関連性の高い追加オーダーを提案。ユーザーのフィードバックを学習することで、提案精度が向上し、医師の業務を効率化します。
- WEB問診内容をAIで分析:問診内容と今までに電子カルテに記載した病名を紐づけ、診察時にAIが病名の候補を表示。導き出した病名より適切な医薬品や検査、画像を提案します。
- 操作性の高い画面: 医療従事者の視点に立ち、直感的で分かりやすい操作画面が特徴です。
- オンプレミス型・クラウド型が選択可能:安定した運用が可能なオンプレミス型、インストール不要のクラウド型を環境に合わせて選べます。
- レセコン一体型: レセプトコンピュータが標準で搭載されています。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 要問い合わせ |
運営会社 | 株式会社ユヤマ |
HPのURL | https://www.yuyama.co.jp/product_category/karte/ |
クラウド型orオンプレミス型orハイブリッド型 | オンプレミス型/クラウド型 |
AI機能 | オーダー内容自動解析(オンプレ型)、WEB問診AI分析機能(クラウド型) |
導入サポート | 要問い合わせ |
周辺システムとの連携・拡張性 | 要問い合わせ |
MI・RA・Is V/+AI(シーエスアイ)
MI・RA・Is V/+AIは、株式会社シーエスアイが提供する電子カルテ「MI・RA・Is V」と、それに連携する文書作成支援AI「MI・RA・Is +AI」です。オンプレミス環境で利用できるAIで、カルテ内容に基づいた文書作成の効率化を支援します。
MI・RA・Is V/+AIの主な特徴
- AIによる文書作成サポート: カルテ内容を元に、AIが文書作成を行います。診療科ごとにプロンプトを設定することも可能です。
- 高い操作性: 直感的で使いやすいインターフェースにより、スムーズな診療をサポートします。
- 大規模病院向け: 複雑な部門システム連携や、病床管理など、病院特有のニーズに対応した機能を備えています。
- 充実した周辺システム連携: 検査システム、画像診断システム、調剤システムなど、病院内の様々な部門システムとの連携が可能です。
- 高い拡張性: 病院の成長や変化するニーズに合わせて、システムを柔軟に拡張できます。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 要問い合わせ |
運営会社 | 株式会社シーエスアイ |
HPのURL | https://www.csiinc.co.jp/solution/mirais-v/ |
クラウド型orオンプレミス型orハイブリッド型 | オンプレミス型/クラウド型 |
AI機能 | 文書作成サポート(MI・RA・Is +AI) |
導入サポート | キックオフから操作研修までサポート |
周辺システムとの連携・拡張性 | 充実した周辺システム連携、高い拡張性 |
homis(メディカルインフォマティクス)
homisは、株式会社メディカルインフォマティクスが提供する訪問・在宅医療に特化したクラウド型電子カルテです。モバイル端末からの操作に最適化されており、インターネット環境がない場所でも入力可能なオフライン機能を搭載。AIで診療情報を解析し、文書作成をサポートする機能も搭載しています。
homisの主な特徴
- AI技術の活用:
これまでの診療情報を自動的に解析し、主治医意見書などをAIが自動作成します。 - 訪問・在宅医療に特化:
訪問先での診療に特化した機能と使いやすさを追求。 - マルチデバイス対応:
スマートフォンやタブレットなど、様々なモバイル端末から利用可能です。 - オフライン入力対応:
インターネット接続がない環境でもカルテ入力ができ、後で自動的に同期されます。 - リアルタイム情報連携:
訪問先で入力した情報がすぐに院内や他医療機関と連携され、多職種連携を円滑にします。 - クラウド型:
サーバー管理不要で、常に最新の機能を利用できます。 - レセコン:
ORCAと連携します。ORCAの導入も可能です。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 200,000円(ORCA導入費別) |
月額費用 | 20,000円~(ORCAサポート料別) |
運営会社 | メディカルインフォマティクス株式会社 |
HPのURL | https://homis-mics.jp/ |
クラウド型orオンプレミス型orハイブリッド型 | クラウド型 |
AI機能 | 文書自動作成 |
導入サポート | ORCAサーバー構築や外部システム連携、オンラインの導入前レクチャー |
周辺システムとの連携・拡張性 | リアルタイム情報連携 |
MegaOak/iS(NECネクサソリューションズ)
MegaOak HR / iSは、NECネクサソリューションズが提供する病院向け電子カルテシステムです。オプション機能「AIメディカルアシスト」により、医療文書作成を支援します。また、地域医療連携の強化や、多職種連携を円滑にする機能が充実しており、病院全体の情報共有と業務効率化を強力に推進します。
MegaOak HR / iSの主な特徴
- AIメディカルアシスト:
電子カルテに記載の診療情報をもとに、紹介状や退院サマリに活用できる文章案を自動生成します。 - 高い信頼性と実績:
長年の実績に裏打ちされた安定したシステムで、病院の基幹業務を支えます。 - 地域医療連携の強化:
他医療機関との情報共有をスムーズにし、地域全体の医療体制強化に貢献します。 - 多職種連携をサポート:
多様な部門システムや職種間での情報共有を円滑にし、チーム医療を促進します。 - 充実した周辺システム連携:
検査システム、画像診断システム、薬剤部門システムなど、病院内の様々なシステムとの連携が可能です。 - 高い拡張性:
病院の規模拡大や機能追加に柔軟に対応できる拡張性を持っています。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 要問い合わせ |
運営会社 | NECネクサソリューションズ株式会社 |
HPのURL | https://jpn.nec.com/medical_healthcare/solution/is/index.html |
クラウド型orオンプレミス型orハイブリッド型 | オンプレミス型 |
AI機能 | 医療文書作成支援 |
導入サポート | 要問い合わせ |
周辺システムとの連携・拡張性 | 充実した周辺システム連携、高い拡張性 |
CLIUS/クリアス(DONUTS)
CLIUSは、IT企業であるDONUTSが開発・提供するクラウド型電子カルテです。高い操作性と、オンライン診療とのスムーズな連携が特徴です。「カルテ作成アシスト機能」でAIが適切なオーダー候補を表示します。特に、オンライン診療の導入を検討しているクリニックにとって、親和性の高い製品と言えます。
CLIUSの主な特徴
- カルテ作成アシスト機能:
所見欄に記載された内容をAIが読み取り、適切なオーダー候補を表示します。 - 直感的な操作性:
Webブラウザで動作するため、PCに不慣れな方でも直感的に操作できます。 - オンライン診療機能:
オンライン診療機能搭載で、予約から診察、処方まで一連の流れを効率化します。 - 充実した経営分析機能:
年次統計、診療時間分析、傷病名分析、リピート率分析など、多角的なデータ分析を通じてクリニックの経営状況を可視化し、集患や経営戦略の改善に貢献します。 - 柔軟な料金体系:
利用規模に応じたプランが用意されており、小規模クリニックでも導入しやすい価格設定です。 - 日本医師会標準レセプトORCAを使用:
ベンダーを変えることなく連携が可能です。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 0円〜(CLIUS Directプラン) |
月額費用 | 19,800円〜(CLIUS Directプラン) |
運営会社 | 株式会社DONUTS |
HPのURL | https://clius.jp/ |
クラウド型orオンプレミス型orハイブリッド型 | クラウド型 |
AI機能 | カルテ作成アシスト機能 |
導入サポート | オンラインでの導入説明、電話・メールサポート |
周辺システムとの連携・拡張性 | オンライン診療連携、充実した経営分析機能 |
その他電子カルテ関連おすすめAIサービス
AIは電子カルテ本体だけでなく、連携するサービスとして診療現場の様々な課題解決に貢献しています。ここでは、電子カルテと連携することでAIの力を最大限に引き出す、おすすめのAIサービスをご紹介します。
kanaVo - AI音声認識文字起こしサービス
kanaVoは、kanata株式会社が提供するAI音声認識文字起こしサービスです。診察時の会話をAIがテキスト化し、要約も可能。コピーして電子カルテへの入力が可能です。医師は手入力の負担から解放され、患者との対話に集中できます。
HPのURL:https://www.kanatato.co.jp/
ユビーAI問診 - AI搭載問診システム
ユビーAI問診は、Ubie株式会社が提供するAI搭載の問診システムです。患者の回答した症状などにより、AIが最適な質問を自動で判断します。質問項目が固定化された従来の問診よりもさらに詳しい質問を行うことができます。
HPのURL:https://ubie.app/about-ai-monshin
今日の問診票 - AI活用問診システム
今日の問診票は、株式会社プレシジョンが提供するAIを活用した問診サービスです。AIが患者の主訴に基づいて動的に質問を追加し、問診結果から考えられる鑑別疾患を提示します。カルテへの転記はコピー&ペーストのみで可能です。
HPのURL:https://www.premedi.co.jp/konnichi-no-monshinhyo/
medimo AI薬歴 - AI薬歴作成サービス
medimo AI薬歴は、株式会社medimoが提供するAI搭載の薬歴作成サービスです。患者との会話を音声認識で文字起こし、AIが SOAP形式に自動要約します。音声を元に、医療用語も正確に書き起こします。
HPのURL:https://medimo.ai/pharmacy
AI搭載の電子カルテの導入事例3選
AI搭載の電子カルテ「エムスリーデジカル」を実際に導入し、成功を収めているクリニックの事例をご紹介します。
えがおクリニック
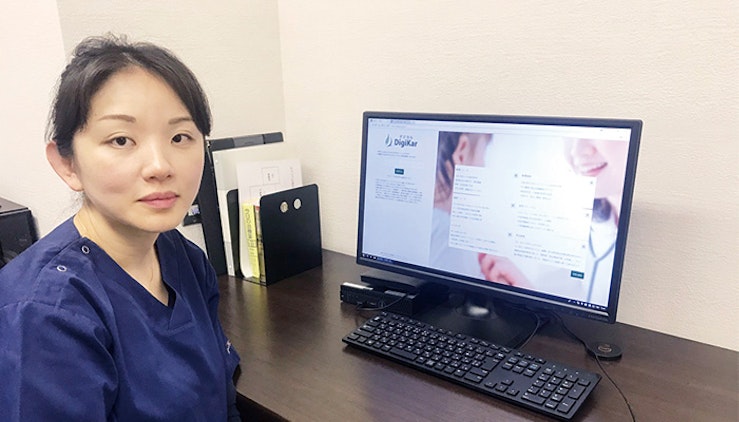
- 内科/ペインクリニック/形成外科
- 新規開業
「開業するにあたり、電子カルテ展示会で候補を絞りました。これまで何種類か使ったことがありましたが、クリニックに不要な機能がなく、シンプルで使いやすいものが良いと考えていました。一緒に働く事務員の使いやすさも重視して選んだのが「デジカル」です。
一番の決め手は、他の電子カルテと比べてデザインが圧倒的にきれいだったことです。普段使っているスマホのアプリのように見やすく、私と事務員の両方が気に入りました。
実際に使ってみると、自動学習機能のおかげで、オーダー入力がとても楽になりました。少し使うだけで、よく使う薬が自動で表示されるので、検索する必要がほとんどありません。他の電子カルテで一般的だった「セット登録」は、デジカルではほとんど行っていません。」
インタビュー全文はこちら
本多記念青野クリニック

- 内科
- 他電子カルテから乗り換え
「友人の医師の紹介でデジカルを知りました。訪問診療との親和性の高さと価格の安さに魅力を感じ、まずは外来での導入を決めました。
実際に使ってみると、シンプルな画面で目が疲れにくく、マニュアルなしで操作を覚えられるほど使いやすいです。カルテの入力は、フリーテキストなのでコピペが簡単にできますし、テンプレートも自分で簡単に作成・修正できるので、以前のようにメーカーに依頼する手間がなく、自分好みのものが作れて便利です。薬の検索も非常に簡単で、入力時間が半分になりました。
AI自動学習機能は患者に処方した薬の組み合わせをAIが自動で学習し表示してくれるので、同じような症状の患者さんには一から入力する必要がなく非常に便利です。私を含め7人の医師が使っていますが、他の医師が登録した処方も表示されるため、処方パターンの参考にもなっています。過去カルテからのコピー入力とこの自動学習リストを併用することで、カルテ作成が非常に効率的になりました。
当初はクラウド型の停止やセキュリティに不安もありましたが、3ヶ月使って一度も止まることはなく、検索速度も以前より速いぐらいです。セキュリティの専門家が管理するクラウド環境のほうが、むしろ安心だと感じています。」
インタビュー全文はこちら
夜間診療所

- 心療内科/精神科
- 他電子カルテから乗り換え
「電子カルテを選ぶ際は、まずクラウド型であること。その中で、デジカルはデモを受けた際の印象が圧倒的に良かったんです。初期費用や月々のコストが希望範囲内だったこと、そしてORCA事業者からサポートを受けられる点も安心でした。
実際に使ってみると、非常に効率よくカルテ作成ができることを実感しています。主訴所見のテンプレートを作成したことで、入力が簡単になりました。デスクトップPCだけでなく、iPadを受付での閲覧用に使うなど、端末を簡単に増やせる点も便利です。
特に役立っているのは、AI自動学習機能です。この機能のおかげで、カルテ入力の時間が大幅に短縮されました。処置行為を学習して使いたい項目を自動表示してくれるので、どんどん入力が楽になっています。初診の患者さんでも2、3分でカルテ作成が完了するほどです。
その他に便利な機能としては、適応症チェックがあります。これのおかげで、薬の査定がほぼなくなりました。また、問診票をPDFでファイルタブに管理できるのも非常に便利ですね」
インタビュー全文はこちら
まとめ
現代の医療現場において、電子カルテの導入は業務効率化や医療の質の向上に不可欠なものとなりつつあり、特にAIを搭載した電子カルテが注目されています。AIは、日々の診療業務を強力にサポートし、医師の負担を大きく軽減します。数多くの製品の中から最適な一つを選ぶためには、AIに何を解決してほしいのか、そして基本的な操作性やサポート体制が自院に合っているかなど、多角的な視点から比較検討することが不可欠です。
この記事でご紹介した各製品の特徴や比較ポイントが、あなたのクリニックのAI搭載電子カルテ導入の成功の一助となれば幸いです。