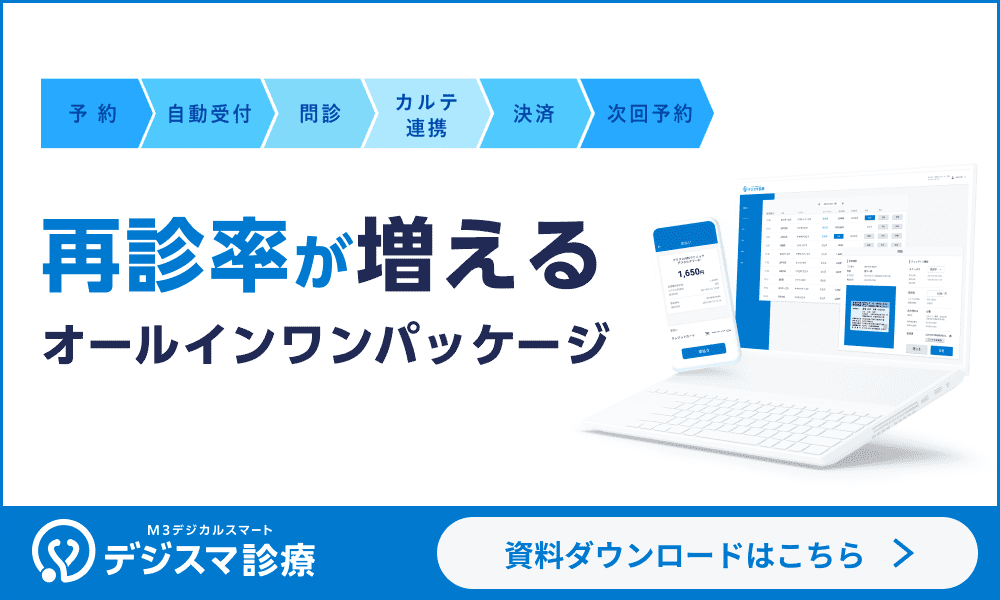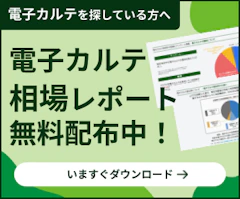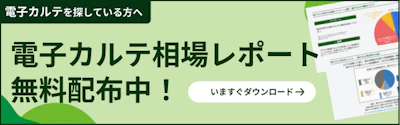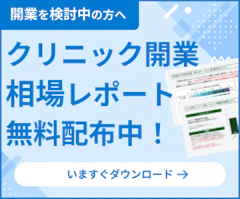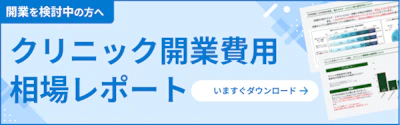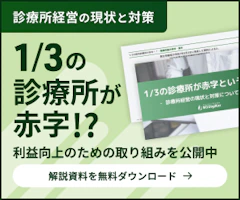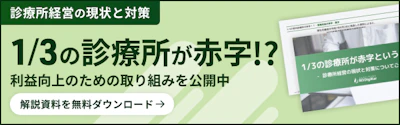【15製品紹介】電子カルテのシェアランキング!クリニック導入メリットと購入の決め手、トレンドや導入ステップを解説
2025年06月30日 更新日: 2026年01月28日
電子カルテ導入を検討中のクリニック必見!最新の電子カルテシェアランキング15製品を徹底解説。導入メリット・デメリット、システム選びの決め手、2025年の最新トレンド、導入ステップまで、クリニック経営者が知るべき情報を網羅。失敗しない電子カルテ選びをサポートします。
目次
医療現場におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の波は、電子カルテの普及を大きく後押ししています。厚生労働省が公表した「医療施設調査」および「病院報告」の結果(令和5年時点)によると、電子カルテの普及率は年々増加傾向にあります。
ここでは、クリニック向けの電子カルテの中から、特にシェア率の高い製品を中心に15製品を紹介します。各製品の主な特徴、初期費用、月額費用、運営会社、クラウド/オンプレミス、導入サポート、レセコン一体型かどうかを比較検討のポイントとしてまとめました。
※この記事は、2025年6月時点の情報に基づいています。
電子カルテの普及率と導入の現状
病院における電子カルテ普及率
病院においては、すでに65.6%(※)の施設で電子カルテが導入されており、大規模病院を中心に導入が進んでいます。これは、診療科が多岐にわたることや、病床数が多いことによる情報共有の複雑さを解消する目的が大きいと考えられます。
クリニックにおける電子カルテ普及率
一方、クリニックにおける電子カルテの普及率は55.0%(※)と、病院に比べてやや低いものの、着実に導入が進んでいます。政府が進める医療DX令和ビジョン2030では、電子カルテの普及率を2030年までに100%にするという目標が掲げられており、今後も導入クリニックの増加が見込まれます。
※参照:診療所のカルテ事情最新レポート
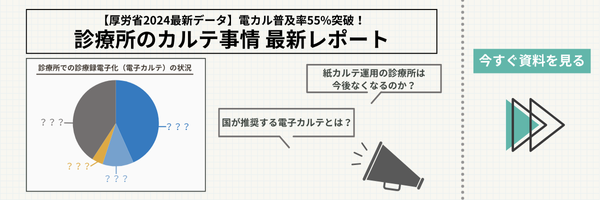
クリニック向け電子カルテのシェアランキング【15製品紹介】
順位 | 製品名 | シェア率 |
|---|---|---|
1位 | エムスリーデジカル/M3DigiKar(エムスリーデジカル) | 25.7% |
2位 | Medicom-HRシリーズ(ウィーメックス) | 15.5% |
3位 | HOPEシリーズ(富士通Japan) | 8.7% |
4位 | Brain Boxシリーズ(ユヤマ) | 3.3% |
5位 | movacal.net/モバカルネット(NTTプレシジョンメディシン) | 3.0% |
5位 | CLIUS/クリアス(Donuts) | 3.0% |
7位 | QUALISシリーズ(ビー・エム・エル) | 2.4% |
7位 | CLINICS(メドレー) | 2.4% |
9位 | Dynamics(ダイナミクス) | 2.1% |
10位 | SUPER Clinicシリーズ(ラボテック) | 1.8% |
10位 | NAVIS-CL(ニデック) | 1.8% |
10位 | MAPs for CLINIC/MRNシリーズ(EMシステムズ) | 1.8% |
参照:https://clinic.m3.com/cliniclab/trends/6.htm
1位:エムスリーデジカル/M3DigiKar(エムスリーデジカル)
シェア率:25.7%
エムスリーデジカルは、医療情報サイト「m3.com」を運営するエムスリーグループが提供するクラウド型電子カルテです。高い操作性と豊富な機能、そして最新のAI技術を活用した業務効率化機能が特徴で、近年特にクリニックからの支持を集め、急速にシェアを拡大しています。
エムスリーデジカルの主な特徴
- 直感的な操作性: 洗練されたUI/UXで、電子カルテの操作に不慣れな方でもスムーズに導入・利用できます。タブレットでの手書き入力や音声入力にも対応し、医師の負担を軽減します。
- AIによる業務支援: よく使う処置行為が自動でセット化されるなど、AIを活用した機能が充実しています。これにより、診察時間の短縮や医療の質の向上に貢献します。
- 「デジスマ診療」とのスムーズな連携: オンライン診療・Web問診・キャッシュレス決済などを一元化できる「デジスマ診療」と連携し、患者さんの予約から診察、会計までを効率化。
- 充実した周辺システム連携: オンライン診療システム、Web予約システム、問診システム、検査システムなど、クリニック運営に必要な様々なシステムとの連携が可能です。
- 強固なセキュリティ体制: 医療情報を扱うため、厳重なセキュリティ対策が施されています。データはクラウド上で管理され、災害時のリスクも低減されます。
- レセコン一体型: レセプトコンピュータが標準で搭載されており、レセプト作成業務を効率化します。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 0円~ |
月額費用 | 11,800円~(ORCA連動型)、24,800円~(レセコン一体型)※いずれも税別 |
運営会社 | 株式会社エムスリーデジカル |
HPのURL | |
システム形態 | クラウド型 |
導入サポート | 専任スタッフによる導入前コンサルティングから導入後のサポートまで手厚い支援 オンライン説明会、セミナーも実施 |
導入周辺システムとの連携・拡張性サポート | 充実した周辺システム連携 |
レセコン | レセコン一体型/ORCA連動型 |
その他、詳しい導入事例や料金プランを確認したい方はこちら

また、エムスリーデジカルは無料で操作性を体験することができます。こちらからご登録ください。
2位:Medicom-HRシリーズ(ウィーメックス株式会社)
シェア率:15.5%
Medicom-HRシリーズは、長年にわたり医療業界で実績を持つウィーメックス(旧PHC)が提供する電子カルテです。全国の医療機関で広く導入されており、安定性と信頼性に定評があります。クラウド型の「Medicom クラウドカルテ」とハイブリッド型の「Medicom-HRf Hybrid Cloud」を提供しており、クリニックの規模やニーズに合わせて選択できる柔軟性が魅力です。
Medicom-HRシリーズの主な特徴
- 豊富な導入実績: 多くの医療機関で利用されており、医療現場のニーズを深く理解した機能が搭載されています。
- 高いカスタマイズ性: クリニックの診療スタイルや業務フローに合わせて、画面や機能を柔軟にカスタマイズできます。
- 強固なセキュリティ: 医療情報を保護するための厳重なセキュリティ対策が講じられています。
- 充実したサポート体制: 導入前から導入後まで、全国に広がるサポート拠点から手厚いサポートが受けられます。
- レセコン一体型: レセプトコンピュータが標準で搭載されており、請求業務を効率化します。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 0円~(Medicom クラウドカルテ) |
月額費用 | 24,800円~(Medicom クラウドカルテ) ※税別 |
運営会社 | ウィーメックス株式会社 |
HPのURL | https://www.phchd.com/jp/medicom/clinics |
システム形態 | クラウド型、ハイブリッド型 |
導入サポート | 全国の拠点からの訪問サポート、電話サポート、オンラインサポート |
周辺システムとの連携・拡張性 | 予約・検査・精算、170社の機器とシームレスにデータ連携が可能 |
レセコン | レセコン一体型 |
3位:HOPEシリーズ(富士通Japan株式会社)
シェア率:8.7%
HOPEシリーズは、IT大手である富士通Japanが提供する医療機関向けソリューションの総称です。電子カルテのHOPE LifeMark-HXやHOPE LifeMark-Clinic IIなど、クリニックの規模や特性に合わせた様々なラインナップを展開しています。大企業ならではの安定したサポートと、最新技術を取り入れた機能開発が特徴です。
HOPEシリーズの主な特徴
- 幅広いラインナップ: 一般診療所から大規模病院まで、様々な医療機関に対応する電子カルテを提供しています。
- 高い信頼性: 長年の実績と富士通の技術力に裏打ちされた、安定したシステムです。
- 最新技術の活用: AIやクラウド技術など、最新のIT技術を積極的に取り入れています。
- 充実した周辺システム連携: 検査システム、画像診断システム、薬局システムなど、幅広いシステムとの連携が可能です。
- レセコン一体型: レセプトコンピュータが標準で搭載されています。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 要問い合わせ |
運営会社 | 富士通Japan株式会社 |
HPのURL | https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/healthcare/hospital-sol/ |
クラウド型orオンプレミス型orハイブリッド型 | クラウド型、オンプレミス型 |
導入サポート | ニーズに応じた導入、運用検討手法の提案 |
周辺システムとの連携・拡張性 | 充実した周辺システム連携 |
レセコン | レセコン一体型 |
4位:Brain Boxシリーズ(株式会社ユヤマ)
シェア率:3.3%
Brain Boxシリーズは、医療機器メーカーであるユヤマが提供する電子カルテです。豊富な医療機器との連携実績があり、クリニックの設備環境に合わせた柔軟なシステム構築が可能です。特に、ユヤマ製の医療機器を導入しているクリニックにはメリットが大きいでしょう。
Brain Boxシリーズの主な特徴
- AIによる診療支援: オーダー内容をAIが自動分析し、関連性の高い追加オーダーを提案。ユーザーのフィードバックを学習することで、提案精度が向上し、医師の業務を効率化します。
- 豊富な薬剤情報データベース: 新世代MDbank総合薬剤データベースを標準搭載。薬の相互作用チェック、適用病名一覧、患者の年齢制限など、意思決定に必要な情報にワンクリックでアクセスでき、安全な処方をサポートします。
- 操作性の高い画面: 医療従事者の視点に立ち、直感的で分かりやすい操作画面が特徴です。
- オンプレミス型・クラウド型が選択可能:安定した運用が可能なオンプレミス型、インストール不要のクラウド型を環境に合わせて選べます。
- レセコン一体型: レセプトコンピュータが標準で搭載されています。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 要問い合わせ |
運営会社 | ユヤマ株式会社 |
HPのURL | |
システム形態 | オンプレミス型/クラウド型 |
導入サポート | 要問い合わせ |
周辺システムとの連携・拡張性 | 要問い合わせ |
レセコン | レセコン一体型 |
また、電子カルテを導入するにあたって、約800名の開業医にアンケートを行い導入費用やランニングコストを調査したレポートを無料でお配りしておりますのでお気軽にご覧ください。
資料ダウンロードはこちら:クリニック向け電子カルテ費用相場レポート
38.1cm%C3%9713.23cm.png)
5位:movacal.net/モバカルネット(NTTプレシジョンメディシン)
シェア率:3.0%
モバカルネットは、NTTプレシジョンメディシン株式会社が提供するクラウド型電子カルテです。在宅医療に特化した機能、強固なセキュリティ、スムーズな連携が特徴。モバイルからのアクセスや効率的な業務支援で、訪問診療を強力にサポートします。
モバカルネットの主な特徴
- 在宅医療特化: モバイルからのアクセスで、在宅医療計画書や訪問看護指示書の一括作成、訪問ルート表示など、訪問診療特有の業務を強力に支援。
- 強固なセキュリティとBCP対策: NTTグループの高セキュリティ技術で、3省2ガイドライン準拠の環境を実現。災害時もデータ復旧体制が整い、安心です。
- 効率的な入力・請求管理: バイタル一括入力に加え、レセプトソフトや介護請求ソフト連携で、請求・収納業務を効率化。
- 柔軟な機能拡張・移行サポート: ユーザー要望を反映した機能開発や、他社からのスムーズなデータ移行をサポートします。
- ORCA連携型: ORCAの導入・運用サポートも行っています。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 200,000円~※税別 |
月額費用 | 50,000円~※税別 |
運営会社 | NTTプレシジョンメディシン株式会社 |
HPのURL | https://movacal.net/ |
システム形態 | クラウド型 |
導入サポート | オンラインでの導入説明、電話・メールサポート |
周辺システムとの連携・拡張性 | スムーズな情報連携、柔軟な機能拡張 |
レセコン | ORCAと連携 |
5位:CLIUS/クリアス(株式会社DONUTS)
シェア率:3.0%
CLIUSは、IT企業であるDONUTSが開発・提供するクラウド型電子カルテです。高い操作性と、オンライン診療とのスムーズな連携が特徴です。特に、オンライン診療の導入を検討しているクリニックにとって、親和性の高い製品と言えます。
CLIUSの主な特徴
- 直感的な操作性: Webブラウザで動作するため、PCに不慣れな方でも直感的に操作できます。
- オンライン診療機能: オンライン診療機能搭載で、予約から診察、処方まで一連の流れを効率化します。
- 充実した経営分析機能: 年次統計、診療時間分析、傷病名分析、リピート率分析など、多角的なデータ分析を通じてクリニックの経営状況を可視化し、集患や経営戦略の改善に貢献します。
- 柔軟な料金体系: 利用規模に応じたプランが用意されており、小規模クリニックでも導入しやすい価格設定です。
- 日本医師会標準レセプトORCAを使用: ベンダーを変えることなく連携が可能です。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 0円〜(CLIUS Directプラン) |
月額費用 | 19,800円〜(CLIUS Directプラン) |
運営会社 | 株式会社DONUTS |
HPのURL | https://clius.jp/ |
システム形態 | クラウド型 |
導入サポート | オンラインでの導入説明、電話・メールサポート |
周辺システムとの連携・拡張性 | オンライン診療連携、充実した経営分析機能 |
レセコン | ORCAを使用 |
7位:Qualisシリーズ(株式会社ビー・エム・エル)
シェア率:2.4%
Qualisシリーズは、臨床検査で長年の実績を持つビー・エム・エルが提供する電子カルテです。検査システムとの連携に強みがあり、検査データの取り込みや管理を効率的に行えます。特に、検査を多く実施するクリニックにおすすめです。
Qualisシリーズの主な特徴
- 検査システム連携に強み: 自社の臨床検査システムとの連携がスムーズで、検査結果を効率的に参照・管理できます。
- 高いセキュリティ: 医療機関のネットワーク環境に合わせたセキュリティ対策が可能です。
- オンプレミス型・クラウド型が選択可能: クリニックの環境に合わせてオンプレミス型・クラウド型のいずれか最適な電子カルテを選べます。
- カスタマイズ性: クリニックの業務フローに合わせて、画面や機能をカスタマイズできます。
- レセコン一体型: レセプトコンピュータが標準で搭載されています。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 要問い合わせ |
運営会社 | ビー・エム・エル株式会社 |
HPのURL | https://www.bml.co.jp/service/qualis/ |
システム形態 | オンプレミス型/クラウド型 |
導入サポート | 導入コンサルティング、設置・設定、保守サポート |
周辺システムとの連携・拡張性 | 検査システム連携に強み |
レセコン | レセコン一体型 |
7位:CLINICS(株式会社メドレー)
シェア率:2.4%
CLINICSは、オンライン診療システムで高い知名度を誇るメドレーが提供するクラウド型電子カルテです。オンライン診療との連携はもちろんのこと、Web予約システムや問診システムなど、患者さんとのコミュニケーションを円滑にする機能が充実しています。
CLINICSの主な特徴
- オンライン診療に強み: オンライン診療システム「CLINICSオンライン診療」とシームレスに連携し、オンライン診療の導入・運用を強力にサポートします。
- 患者体験の向上:「CLINICS予約」「CLINICS問診」との連携で患者さんの利便性を高めます。
- シンプルな操作性: 直感的な操作で、誰でも簡単に使いこなせるよう設計されています。
- 継続的な機能改善: ユーザーの声を取り入れ、定期的に機能のアップデートが行われています。
- レセコン一体型: レセプトコンピュータが標準で搭載されています。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 0円~ |
月額費用 | 要問い合わせ |
運営会社 | 株式会社メドレー |
HPのURL | https://clinics-cloud.com/karte |
システム形態 | クラウド型 |
導入サポート | 導入支援オプションあり |
周辺システムとの連携・拡張性 | オンライン診療連携、Web予約システム、問診システム連携ほか |
レセコン | レセコン一体型 |
9位:Dynamics(ダイナミクス)
シェア率:2.1%
Dynamicsは、株式会社ダイナミクスが提供するオンプレミス型の電子カルテです。導入・運用コストが安価である点が大きな特徴で、コストパフォーマンスを重視するクリニックにとって魅力的な選択肢となります。
Dynamicsの主な特徴
- 安価な導入・運用コスト: 導入費用および月々の運用コストが抑えられているため、予算を重視するクリニックに適しています。
- 手厚いサポート体制: 導入後のトラブルや疑問に対し、充実したサポートが提供されており、安心して運用できます。
- 多機能な診療・受付支援: 診察ラベル機能や予約管理、各種セット機能で、患者状況管理やカルテ入力を効率化します。
- 訪問診療・モバイル対応: 訪問先でのデータ閲覧・入力や、スマートフォン・iPadからの参照が可能。災害時の備えとしても活用できます。
- レセコン一体型: レセプトコンピュータが標準で搭載されています。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 220,000円※税込 |
月額費用 | 13,200円※税込 |
運営会社 | 株式会社ダイナミクス |
HPのURL | https://www.superdyn.jp/ |
システム形態 | オンプレミス型 |
導入サポート | 導入時訪問インストラクションあり(有料) |
周辺システムとの連携・拡張性 | 多機能な診療・受付支援、訪問診療・モバイル対応 |
レセコン | レセコン一体型 |
10位:SUPER CLINICシリーズ(株式会社ラボテック)
シェア率:1.8%
SUPER CLINICシリーズは、長年の実績を持つラボテックが提供する電子カルテです。従来の紙カルテのような直感的な操作性と高速なレスポンスを追求し、クリニックの業務効率化とスムーズな診療を強力にサポートします。
SUPER CLINICシリーズの主な特徴
- 紙カルテのような直感的な操作性: 従来の紙カルテのような見やすい画面レイアウトで、過去の記録と現在の記録を並べて表示できます。
- 高速なレスポンスと業務効率化: データ検索や画面遷移の遅延を最小限に抑えた素早い操作によりクリニック全体の業務効率を向上させます。
- 充実した外部連携機能: 様々な外部システムや医療機器とのシームレスな連携に対応し、クリニックの運用をさらに効率化します。
- オンプレミス型: 院内にサーバーを設置するため、安定した運用が可能です。
- レセコン一体型: レセプトコンピュータが標準で搭載されています。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 要問い合わせ |
運営会社 | 株式会社ラボテック |
HPのURL | https://labotech.jp/products/ |
クラウド型orオンプレミス型orハイブリッド型 | オンプレミス型 |
導入サポート | 導入コンサルティング、システム設定、操作指導、保守サポート |
周辺システムとの連携・拡張性 | 充実した外部連携機能 |
レセコン | レセコン一体型 |
また、電子カルテを導入するにあたって、約800名の開業医にアンケートを行い導入費用やランニングコストを調査したレポートを無料でお配りしておりますのでお気軽にご覧ください。
資料ダウンロードはこちら:クリニック向け電子カルテ費用相場レポート
38.1cm%C3%9713.23cm.png)
10位:NAVIS-CL(ニデック)
シェア率:1.8%
NAVIS-CLは、株式会社ニデックが提供するオンプレミス型の電子カルテです。ユーザーインターフェース(UI)の良さに定評があり、直感的で使いやすい画面設計が特徴です。診療の流れに沿ったスムーズな操作で業務効率化を追求し、眼科領域での豊富な実績を持つニデックならではの視点から、医療現場のニーズに応える設計がされています。
NAVIS-CLの主な特徴
- 優れたインターフェースと操作性: 直感的で分かりやすい画面設計とスムーズな操作性で、日々の診療業務を効率化します。
- 業務のスムーズな進行: 診療の流れに沿った設計により、無駄のない操作で業務を滞りなく進められます。
- オンプレミス型: 院内サーバーでの運用により、インターネット環境に左右されず安定した稼働が可能です。
- ORCA連携型: レセプトコンピュータはORCAと連携して利用します。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 要問い合わせ |
月額費用 | 要問い合わせ |
運営会社 | 株式会社ニデック |
HPのURL | https://www.nidek.co.jp/items/solution_system_navis-cl/ |
クラウド型orオンプレミス型orハイブリッド型 | オンプレミス型 |
導入サポート | 要問い合わせ |
周辺システムとの連携・拡張性 | 要問い合わせ |
レセコン | ORCAと連携 |
10位:MAPs for CLINIC/MRNシリーズ(株式会社EMシステムズ)
シェア率:1.8%
EMシステムズは、調剤薬局システムで高いシェアを誇る企業であり、そのノウハウを活かした電子カルテを提供しています。MAPs for CLINICとMRNシリーズは、それぞれ異なる特徴を持つラインナップで、クリニックのニーズに合わせた選択が可能です。
MAPs for CLINIC/MRNシリーズの主な特徴
- 直感的な操作性と効率的な画面レイアウト: シンプルで分かりやすい画面設計により、日々の診療業務を効率化します。
- 柔軟なカスタマイズ性: クリニックの運用に合わせて、画面や機能をカスタマイズできます。
- 充実した入力支援機能: 病名候補アシスト機能など、スムーズなカルテ入力をサポートします。(MRNシリーズ)
- 安心のサポート体制: 導入前から導入後まで、全国のサポート拠点から手厚いサポートが受けられます。
- レセコン一体型: レセプトコンピュータが標準で搭載されています。
項目 | 詳細 |
|---|---|
初期費用 | 0円~(MAPs for CLINIC) |
月額費用 | 20,000円~(MAPs for CLINIC) ※税別 |
運営会社 | 株式会社EMシステムズ |
HPのURL | https://emsystems.co.jp/ |
クラウド型orオンプレミス型orハイブリッド型 | クラウド型 |
導入サポート | 専任担当者による導入支援、ヘルプデスク |
周辺システムとの連携・拡張性 | 幅広い周辺システム連携、柔軟な機能拡張性 |
レセコン | レセコン一体型 |
その他電子カルテの紹介
近年は、AI技術の活用や、特定の診療スタイルに特化した電子カルテも登場しています。ここでは、注目すべき新しい電子カルテをいくつかご紹介します。
Open-Karte Cloud(ウィーメックス ヘルスケアシステムズ株式会社)
Open-Karte Cloudは、日医標準レセプトソフト「ORCA」と連携するクラウド型電子カルテです。アシストビュー機能が特徴で、診療中に必要な情報をまとめて表示することで、効率的な診療をサポートします。ORCAとの連携により、レセプト業務をスムーズに行える点も魅力です。
主な特徴: アシストビュー機能、ORCA連携、クラウド型、レセコン一体型。
HPのURL:https://www.hs.wemex.com/medical/open-karte-cloud
blanc(亀田医療情報株式会社)
blancは、遠隔診療や訪問診療・看護のワークフローにもフィットするよう設計されたクラウド型電子カルテです。職種ごとに最適化された機能メニューを提供し、診察室、病室、訪問先など場所を問わず、一貫した使用感で医療情報へのアクセスと入力が可能。訪問先で登録した情報をリアルタイムで病院・薬局と連携することで、次世代の医療サービス提供を強力にサポートします。
主な特徴: 遠隔診療・訪問診療対応、地域医療連携、クラウド型、レセコン一体型。
HPのURL:https://site.blanc-karte.jp/
セコム・ユビキタス電子カルテ(セコム医療システム株式会社)
セコム・ユビキタス電子カルテは、セキュリティ大手であるセコムグループが提供するクラウド型電子カルテです。セコムの強固なセキュリティ技術とノウハウを活かし、患者情報の保護に特化。多様な医療機関の運用に対応し、情報漏洩リスクを最小限に抑えたいクリニックに最適です。
主な特徴:最高レベルのセキュリティ、多様な医療機関に対応、クラウド型、レセコン一体型。
HPのURL:https://medical.secom.co.jp/it/karte/ubiquitous/
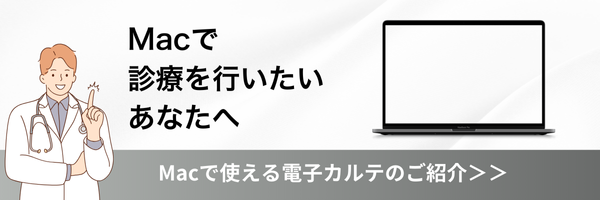
電子カルテ導入のメリット・デメリット
電子カルテの導入は、クリニックの運営に大きな変化をもたらします。導入を検討する際には、そのメリットとデメリットを十分に理解しておくことが重要です。
電子カルテ導入のメリット
- 業務効率の向上: 手書きカルテの記入、保管、検索にかかる時間を大幅に短縮できます。レセプト作成も自動化され、事務作業の負担が軽減されます。
- 医療安全の向上: 判読性の高いデータで記入ミスや読み間違いが減り、医療事故のリスクを低減します。アレルギー情報や禁忌薬の自動警告機能なども活用できます。
- 情報共有の円滑化: 医師、看護師、医療事務などのスタッフ間でリアルタイムに患者情報を共有できます。これにより、チーム医療が促進されます。
- 経営状況の把握: 診療データがデジタル化されるため、疾患別、月別などの集計・分析が容易に行えます。これにより、経営改善のための具体的な施策を検討しやすくなります。
- 省スペース化: 紙カルテの保管場所が不要になり、クリニック内のスペースを有効活用できます。
- 患者サービスの向上: 待ち時間の短縮、オンライン予約システムの導入、オンライン診療の実施などにより、患者さんの利便性が向上します。
- 災害時対策: クラウド型電子カルテであれば、災害時にもデータが保護され、別の場所からアクセスできるため、診療の継続性が確保されます。
電子カルテ導入のデメリット
- 初期費用と月額費用: システム導入には初期費用や月額費用がかかります。PCや周辺機器の購入費用も考慮する必要があります。
- 操作習熟までの時間: 電子カルテの操作に慣れるまでに、医師やスタッフの一定の学習期間が必要です。
- システムトラブルのリスク: システム障害やネットワークトラブルが発生した場合、一時的に診療が滞る可能性があります。クラウド型の場合はインターネット環境に依存します。
- 情報漏洩のリスク: サイバー攻撃やヒューマンエラーによる情報漏洩のリスクがゼロではありません。セキュリティ対策が重要になります。
- 停電時の対応: 停電が発生した場合、システムが利用できなくなる可能性があります。緊急時の対応策を検討しておく必要があります。
- 法改正への対応: 医療に関する法改正があった場合、電子カルテシステムもそれに合わせてアップデートされる必要があります。ベンダーの対応力を確認することが重要です。
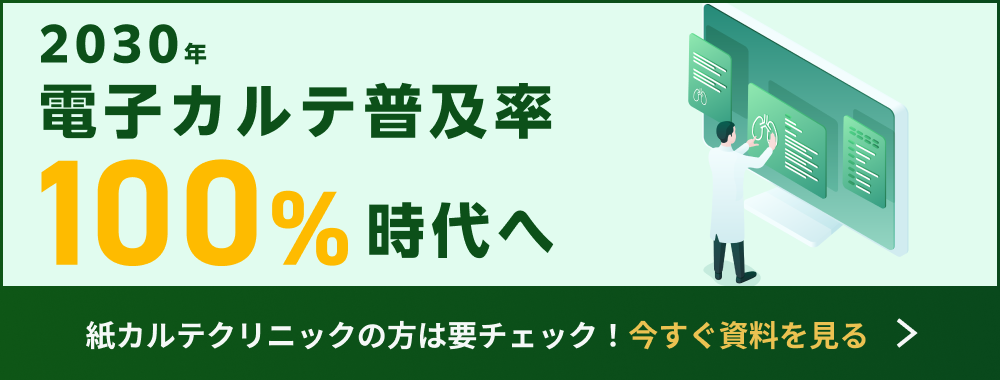
クリニック向け電子カルテの選び方・比較するポイント
電子カルテはクリニックの「顔」とも言える重要なシステムです。多種多様な製品の中から、自院に最適なものを選ぶためには、いくつかの比較ポイントを押さえる必要があります。
クリニック向け電子カルテの選び方・比較するポイント① 業務フローへの適合
電子カルテは、毎日の診療業務に直接関わるシステムです。そのため、自院の診療科や診療スタイル、スタッフの業務フローに適合しているかを最も重視すべきです。
- 専門診療科特化型か汎用型か: 例えば眼科や産婦人科など、専門性の高い診療科であれば、その科に特化した機能を持つ電子カルテという選択肢もあります。
- カルテの記載形式と入力速度: 普段のカルテ記載方法に近い入力形式か、あるいは手書きや音声入力などの補助機能が充実しているかを確認しましょう。
- 既存の業務フローを改善できるか: 現状の課題(待ち時間が長い、レセプトに時間がかかるなど)を解決し、よりスムーズな運用を実現できる機能があるか検討しましょう。
クリニック向け電子カルテの選び方・比較するポイント② 操作性
日々使うものだからこそ、直感的でストレスなく操作できるかは非常に重要です。全スタッフがスムーズに使いこなせるシステムを選ぶことで、導入後の混乱を最小限に抑え、診療に集中できる環境を整えることができます。
- デモや無料体験の活用: 実際に触ってみて、画面の見やすさ、ボタンの配置、入力のしやすさなどを確認しましょう。
- 入力補助機能の有無: 定型文入力、予測変換、音声入力、手書き入力、AI活用など、入力の手間を省く機能が充実しているか確認しましょう。
- スタッフの意見: 医師だけでなく、看護師や医療事務スタッフなど、実際に使用する全員の意見を聞き、使いやすさを評価しましょう。
クリニック向け電子カルテの選び方・比較するポイント③ クラウド型かオンプレミス型か
電子カルテのシステム形態は大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自院に合った方を選びましょう。
クラウド型電子カルテのメリット・デメリット
メリット
- 初期費用が安い:サーバーの購入や設置が不要なため、初期費用を抑えられます。
- 場所を選ばない:インターネット環境があれば、どこからでもアクセス可能です(自宅、出張先など)。往診や訪問診療を行うクリニックに適しています。
- メンテナンス不要:システムの保守・管理はベンダーが行うため、クリニック側の負担がありません。
- 常に最新版:自動的にアップデートされるため、常に最新の機能や法改正に対応したシステムを利用できます。
- 災害対策: データがクラウド上に保存されるため、災害時も安心です。
デメリット
- インターネット環境に依存: インターネット接続がないと利用できません。安定した通信環境の確保が必要です。
- ランニングコスト:月額利用料がかかります。
- カスタマイズの制限:オンプレミス型に比べ、カスタマイズの自由度が低い場合があります。
オンプレミス型電子カルテのメリット・デメリット
メリット
- カスタマイズの自由度が高い: 自院のニーズに合わせて、システムを細かくカスタマイズできます。特定の診療科に特化した運用や、既存システムとの連携を重視する場合に有利です。
- インターネット環境に依存しない:院内ネットワークで完結するため、インターネット環境の影響を受けず、安定した運用が可能です。
デメリット
- 初期費用が高い: サーバーやネットワーク機器の購入、設置費用がかかります。
- 運用・保守管理の負担:システムの保守・管理は自院で行うか、外部に委託する必要があり、専門知識やコストが発生します。
- バージョンアップ:新機能の導入や法改正への対応には、別途費用や作業が必要です。
- 災害対策:院内サーバーのため、災害時のデータ保護には別途対策が必要です。
クリニック向け電子カルテの選び方・比較するポイント④ セキュリティ要件
患者さんの重要な医療情報を扱うため、セキュリティ対策は最も重要な比較ポイントの一つです。強固なセキュリティ対策が講じられているシステムを選ぶことは、クリニックの信頼性にも直結します。
- データ暗号化: データの送受信や保管時に強固な暗号化が施されているかを確認しましょう。
- アクセス権限管理: 誰がどの情報にアクセスできるかを細かく設定し、不適切なアクセスを防ぐ機能があるかを確認しましょう。
- バックアップ体制: 定期的なデータバックアップが行われているか、万が一のシステム障害や災害時に迅速にデータを復旧できる体制が整っているかを確認しましょう。
- 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証:ベンダーがISMS認証を取得しているか、第三者機関によるセキュリティ監査を定期的に受けているかなども、信頼性を判断する材料になります。
- 物理的セキュリティ:オンプレミス型の場合は、サーバーが設置される場所の物理的セキュリティ(入退室管理、耐震・防火対策など)も確認しましょう。
クリニック向け電子カルテの選び方・比較するポイント⑤ 周辺システムとの連携・拡張性
電子カルテは単体で機能するものではなく、他のシステムとの連携によって真価を発揮します。円滑な医療連携や業務効率化のためには、連携性も重要な選定基準です。
- レセプトコンピュータ(レセコン)一体型: 多くの電子カルテはレセコン一体型ですが、そうでない場合は別途レセコンの導入が必要になります。一体型の方が業務は効率的であり、エラーも発生しにくくなります。
- オンライン診療システムとの連携:今後のオンライン診療の導入を検討している場合は、スムーズに連携できるか確認しましょう。
- Web予約システム・Web問診システムとの連携: 患者さんの利便性向上に繋がるこれらのシステムとの連携も重要です。患者情報が自動でカルテに反映されることで、入力の手間が省けます。
- 会計システムとの連携: 検査データや画像データをスムーズに取り込み、カルテに反映できるか、過去データを一元的に管理できるかを確認しましょう。
- 医療連携の相互運用性: 会計業務を効率化するために、電子カルテと連携できる会計システムを選びましょう。
- 将来的な拡張性: 将来的にクリニックの規模が拡大したり、新たな診療スタイルを導入したりする際に、柔軟に機能や連携システムを拡張できるシステムかを確認しましょう。
クリニック向け電子カルテの選び方・比較するポイント⑥ 導入サポート体制と費用対効果
電子カルテの導入は、クリニックにとって大きなプロジェクトです。ベンダーのサポート体制は非常に重要であり、長期的な運用を見据えた費用対効果も考慮すべきです。
- レセプトコンピュータ(レセコン)一体型: 多くの電子カルテはレセコン一体型ですが、そうでない場合は別途レセコンの導入が必要になります。一体型の方が業務は効率的であり、エラーも発生しにくくなります。
- 導入前のコンサルティングクリニックの現状をヒアリングし、最適なシステム構成を提案してくれるか。
- 導入時の設定・初期指導 システムの設置、初期設定、操作指導などを丁寧に行ってくれるか。
- 導入後のサポート: 稼働後のトラブル対応、操作に関する問い合わせ、法改正への対応など、継続的なサポートが充実しているか。困ったときにすぐに相談できる窓口があるかは、日々の業務の安心感に繋がります。
- サポート時間・窓口: 診療時間外や緊急時にも対応してくれるサポートがあるか、電話、メール、リモートなど、複数の問い合わせ窓口があるか。
- 費用: サポート費用が月額費用に含まれるのか、別途費用が発生するのかを確認しましょう。初期費用だけでなく、月額利用料、保守費用、バージョンアップ費用なども含めた長期的な費用対効果を検討することが重要です。
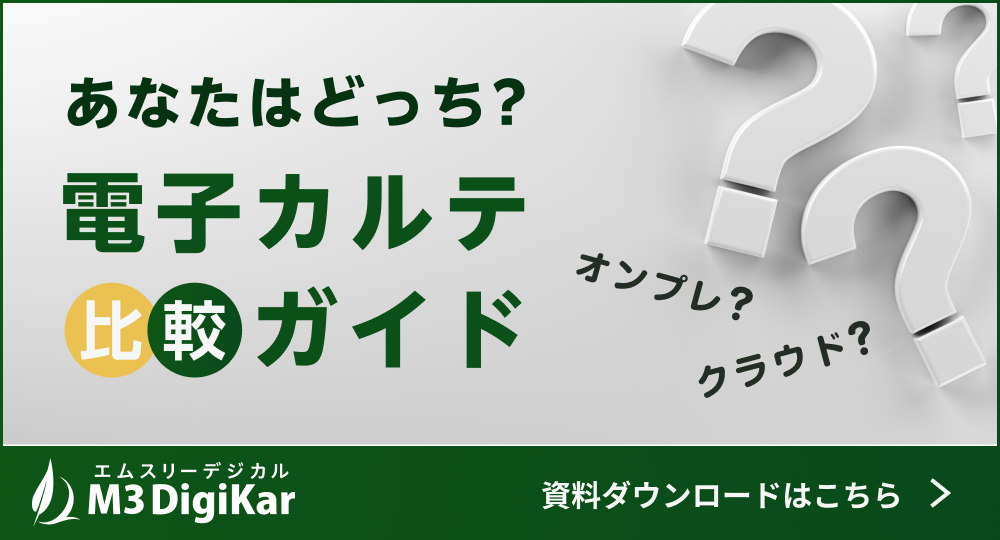
クリニック向け電子カルテの購入の決め手TOP5
多くのクリニックが電子カルテを導入する際、何を最も重視しているのでしょうか。m3.comの調査データ(2023年時点)に基づいた、電子カルテ購入の決め手TOP5をご紹介します。 これらのポイントは、実際に電子カルテを導入したクリニックの生の声であり、あなたの選定に役立つでしょう。
1位:クラウド型であること(8.9%)
導入の決め手として最も多く挙げられたのが「クラウド型であること」でした。サーバー設置が不要で初期費用を抑えられ、インターネット環境があればどこからでもアクセスできる手軽さが魅力です。
- 選ばれる理由:
サーバー設置が不要で初期費用を抑えられ、インターネット環境があればどこからでもアクセスできる手軽さが魅力です。システムのメンテナンスやバージョンアップもベンダーが行うため、運用負担が大幅に軽減されます。また、災害時にもデータが安全に保護されるというBCP(事業継続計画)の観点も重視されています。 - 該当製品の例:
エムスリーデジカル、CLIUS、CLINICS、セコム・ユビキタス電子カルテ、モバカルネットなどがクラウド型に該当します。
2位:入力のしやすさ(8.4%)
次に重視されるのが「入力のしやすさ」です。日々の診療で医師やスタッフがストレスなく、効率的にカルテを記載できるかが、電子カルテ活用の成否を分けます。
- 選ばれる理由:
直感的な操作画面、定型文の登録機能、音声入力や手書き入力への対応など、入力作業を補助する機能の充実度が求められます。これにより、診察時間の短縮や医療の質の向上に繋がります。 - 該当製品の例:
エムスリーデジカルやMedicom-HRシリーズは、その入力のしやすさで高い評価を得ています。
3位:ランニングコスト(7.5%)
導入後の「ランニングコスト」も重要な決め手となります。初期費用だけでなく、月々の運用コストが予算に合っているか、長期的な費用対効果が見込めるかが判断されます。
- 選ばれる理由:
月額利用料、保守費用、バージョンアップ費用など、継続的に発生する費用が明確であり、クリニックの経営状況に無理なく組み込めるかが重視されます。 - 該当製品の例:
リモートでのサポートが中心のプランがあるメーカーは月額費用を抑えられる傾向にあります。
4位:導入サポート(6.1%)
電子カルテ導入はクリニックにとって大きな変化を伴うため、「導入サポート」の手厚さも重要な決め手となります。
- 選ばれる理由:
導入前のコンサルティングから、システム設定、操作指導、そして稼働後のトラブル対応まで、ベンダーがどれだけ手厚くサポートしてくれるかが重視されます。特に、ITに不慣れなスタッフが多い場合や、初めての電子カルテ導入では、きめ細やかなサポートが不可欠です。地域に密着したサポート体制も安心材料となります。 - 該当製品の例:
各社、導入サポートには力を入れていますが、特に地域拠点の多いMedicom-HRシリーズやHOPEシリーズなどは強みとしています。
5位:レセコン一体型(5.9%)
「レセプトコンピュータ一体型」であることも、多くのクリニックが重視するポイントです。診療記録とレセプト作成が同一システム内で完結することで、業務効率が大幅に向上します。
- 選ばれる理由:
診療記録とレセプト作成が同一システム内で完結することで、入力の二度手間がなくなり、業務効率が大幅に向上します。また、カルテとレセプト間の整合性が保たれやすく、ヒューマンエラーによる請求ミスを減らすことにも繋がります。 - 該当製品の例:
本記事で紹介しているほとんどの電子カルテはレセコン一体型であり、これはクリニック向け電子カルテの標準的な機能となっています。
電子カルテ導入のトレンド
電子カルテの技術は日々進化しており、クリニックの運営を取り巻く環境の変化とともに、新たなトレンドが生まれています。
- AI・音声認識技術の活用: 診察中の会話を自動でテキスト化したり、AIが適切な病名や処方内容を提案したりする機能が進化しています。これにより、医師のカルテ入力時間を大幅に短縮し、診療に集中できる環境を整えます。
- オンライン診療・遠隔医療との連携強化: コロナ禍を経て普及したオンライン診療は、今後も重要な診療形態として定着していくと予想されます。電子カルテとオンライン診療システムがシームレスに連携し、予約から診察、処方、会計まで一貫したワークフローを提供できる製品が求められています。
- データ連携・地域医療連携の推進: 他の医療機関や薬局とのデータ連携を強化し、患者さんの医療情報を共有することで、より質の高い医療提供を目指す動きが加速しています。地域医療連携ネットワークへの対応や、PHR(Personal Health Record)との連携も注目されています。
- モバイル端末対応の強化: 医療従事者がストレスなく操作できるよう、より直感的でシンプルなユーザーインターフェース(UI)と、快適なユーザーエクスペリエンス(UX)を提供する電子カルテが増えています。
- UX/UIの洗練: スマートフォンやタブレットから電子カルテにアクセスできることで、往診や訪問診療など、院外での診療時にもリアルタイムでカルテ入力や情報参照が可能になります。
- クラウド化の加速: 初期費用を抑えられ、メンテナンス不要で常に最新の機能を利用できるクラウド型電子カルテの導入がさらに進むでしょう。災害対策やセキュリティの観点からもクラウドの優位性が認識されています。
また、電子カルテを導入するにあたって、約800名の開業医にアンケートを行い導入費用やランニングコストを調査したレポートを無料でお配りしておりますのでお気軽にご覧ください。
資料ダウンロードはこちら:クリニック向け電子カルテ費用相場レポート
38.1cm%C3%9713.23cm.png)
電子カルテ導入の流れ・ステップ
電子カルテの導入は、クリニックにとって大きなプロジェクトです。計画的に進めることでスムーズに行うことができます。ここでは、一般的な導入ステップと、各ステップのゴール、アクション概要、所要期間を解説します。
ステップ1:検討・情報収集(導入2年~1年前)
ゴール
自院のニーズと課題を明確にし、電子カルテに関する基礎知識と候補製品情報を網羅的に把握する。
主なアクション
- 現状分析と課題抽出: 現行の紙カルテ運用における問題点(保管場所、検索性、レセプト業務の負担など)や、電子カルテ導入によって解決したい具体的な課題をリストアップします。
- 導入目的の明確化: 「なぜ電子カルテを導入するのか」「導入によって何を達成したいのか」といった目的を明確にすることで、後工程の製品選定や導入計画がスムーズになります。
- 予算設定: 初期費用、月額費用、PCやプリンター、ネットワーク機器などの周辺機器費用を含めた予算の目安を設定します。
- 情報収集: インターネットでの情報検索、医療IT展示会への参加、他院へのヒアリングなどを通じて、電子カルテの製品情報や導入事例を収集します。特に、自院の診療科や規模に近いクリニックの導入事例は参考になります。
- 比較検討項目の洗い出し: 前述の「選び方・比較するポイント」を参考に、自院にとって特に重要な比較項目(クラウドかオンプレミスか、レセコン一体型か、サポート体制など)を明確にします。
所要期間:1ヶ月〜6ヶ月
ステップ2:事前ヒアリング・機種選定(導入1年~6ヶ月前)
ゴール
クリニックの運用イメージをベンダーに伝え、デモンストレーションを通じて最適な電子カルテを選定する。
主なアクション
- 候補製品の絞り込み: 情報収集で得たデータをもとに、複数の候補製品を5つ程度に絞り込みます。
- ベンダーへの事前ヒアリング: 絞り込んだ候補製品のベンダーに連絡を取り、自院の診療科、患者数、スタッフ構成、既存の業務フローや課題などを詳細に伝え、自院の運用イメージを共有します。
- 製品デモンストレーションの依頼: ベンダーにデモンストレーションを依頼し、実際の操作画面や機能を体験します。可能であれば、医師だけでなく、看護師や医療事務スタッフも参加し、全員で操作性や使いやすさを評価しましょう。無料トライアルがあれば積極的に活用し、実践的な使用感を確かめることが重要です。
- 見積もり取得: 複数のベンダーから、詳細な見積もり(初期費用、月額費用、オプション費用、サポート費用など)を取得し、機能と価格のバランスを比較検討します。
- 質疑応答・交渉: 疑問点や不安な点(システムトラブル時の対応、データバックアップ、法改正への対応など)をベンダーに確認し、サポート体制や費用面での交渉を行います。
所要期間:1ヶ月〜6ヶ月
ステップ3:導入契約・環境準備(導入6ヶ月~4ヶ月前)
ゴール
選定した電子カルテの正式契約を締結し、システム稼働に必要な環境を整える。
主なアクション
- 最終選定・契約: 比較検討の結果、最も自院に適した電子カルテを最終的に選定し、ベンダーと正式な導入契約を締結します。
- システム環境構築: ベンダーと連携し、サーバーの設置(オンプレミス型の場合)、PC・モニター・プリンター・スキャナーなどの周辺機器の選定と設置、高速なインターネット回線の導入や院内ネットワーク環境の整備を行います。
- 初期設定・データ移行: 診療科情報、医師情報、患者基本情報、病名マスター、医薬品マスターなどの初期設定を行います。必要であれば、既存の紙カルテや旧システムからの患者データ(基本情報、既往歴、アレルギー情報など)の移行作業を進めます。紙カルテの場合は、必要に応じてスキャン作業なども行います。
所要期間:2週間〜4ヶ月
ステップ4:スタッフ研修・運用テスト(導入2ヶ月~1ヶ月前)
ゴール
全スタッフが電子カルテの基本操作を習得し、実際の運用に近い形でテストを行うことで問題点を洗い出す。
主なアクション
- スタッフ研修: 医師、看護師、医療事務など、実際に電子カルテを使用する全スタッフを対象に、ベンダーによる操作研修を実施します。カルテ入力、処方箋発行、会計処理、レセプト作成など、それぞれの役割に応じた操作方法を習得します。操作マニュアルの配布や作成も行い、いつでも参照できる環境を整えます。
- 運用テスト: 研修で習得した知識をもとに、少数のダミー患者データを使用し、実際の診療を想定した運用テストを行います。予約受付から診察、処方、会計、レセプト作成までの一連の業務フローを試し、スムーズに流れるか、不具合はないかを確認します。
所要期間:2週間〜1ヶ月
ステップ5:ロールプレイングによる最終確認(導入2週間前~直前)
ゴール
本稼働に向けて、実際の診療に近い形で最終的な動作確認とスタッフ間の連携確認を行う。
主なアクション
- 本格的なロールプレイング: 実際の開院日を想定し、受付から診察室、会計まで、スタッフがそれぞれの役割を演じながら、患者さんの来院から診察、会計、帰宅までの一連の診療フローを電子カルテで再現します。
- 課題の洗い出しと改善: ロールプレイング中に発生した疑問点や操作上の課題、システムの不具合などをその場で確認し、ベンダーに問い合わせたり、運用フローを調整したりして改善を図ります。特に、緊急時の対応や、予期せぬ事態への対処方法なども確認しておきましょう。
- スタッフ間の連携確認: 電子カルテ導入によって変化するスタッフ間の連携方法を再確認し、情報共有の漏れがないか、スムーズなコミュニケーションが取れるかを確認します。
所要期間:1週間〜2週間
ステップ6:本格稼働開始(導入当日)
ゴール
電子カルテシステムを正式に稼働させ、日常診療での運用を開始する。
主なアクション
- 最終チェック: ロールプレイングで問題がなかったことを確認し、電子カルテシステムを本稼働させます。
- 運用開始: 実際の患者さんを対象に、電子カルテを使用した診療を開始します。
- ベンダーの立ち会い・オンサイトサポート: 稼働開始直後は、予期せぬトラブルが発生しやすい期間です。可能であれば、ベンダーの担当者に立ち会ってもらい、操作に関する質問やトラブルに迅速に対応してもらえる体制を整えましょう。
- 継続的な改善: 稼働後も、実際に運用する中で気づいた改善点や効率化できる点があれば、定期的にスタッフ間で共有し、ベンダーと連携しながらシステムや運用フローの改善を図っていくことが重要です。
所要期間:導入当日〜継続的
まとめ
電子カルテの導入は、クリニックの業務効率化、医療安全の向上、そして患者サービスの質向上に大きく貢献します。数多くの製品の中から最適な一つを選ぶためには、自院のニーズを明確にし、多角的な視点から比較検討することが不可欠です。
この記事でご紹介したシェアランキングや比較ポイント、導入ステップが、あなたのクリニックの電子カルテ導入の成功の一助となれば幸いです。
どのような電子カルテがあなたのクリニックに最もフィットするか、ぜひこの機会にじっくりと検討してみてください。